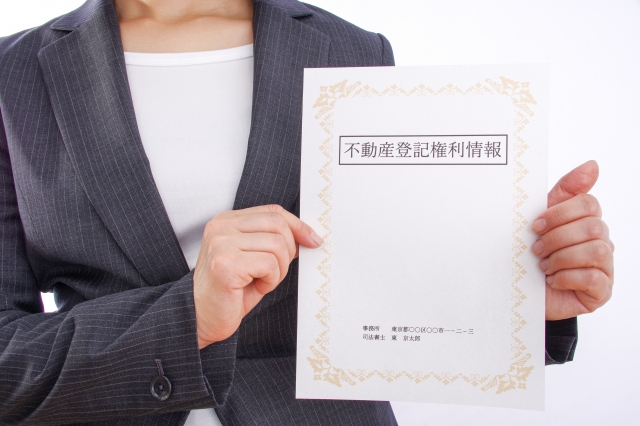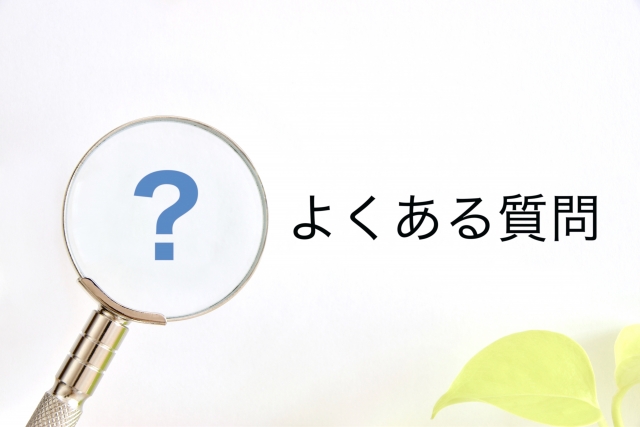近年、空き家の増加が社会問題となっており、適切な管理や活用を促進するために、さまざまな税制優遇措置が設けられています。
一方で、空き家をほっておくと、逆に税制優遇がなくなり、税金が高くなることもあります。以下空き家関連に関する税制優遇についてまとめてみました。
◆固定資産税の軽減措置

住宅が建っている土地(住宅用地)には、固定資産税および都市計画税の軽減措置が適用されます。
①小規模住宅用地(200㎡以下):課税標準額が1/6に軽減
②一般住宅用地(200㎡超):課税標準額が1/3に軽減
ただし、適切に管理されていない空き家が「特定空家等」に指定されると、この軽減措置が解除され、固定資産税が最大6倍に増額される可能性があります。
そのため、相続した空き家をずっとそのままにしておくと、行政から「特定空家等」に認定され、毎年の固定資産税だけでもかなりの出費となってしまいます。
◆相続した空き家の売却に関する特例

相続により取得した空き家を一定の条件のもと売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。
①対象となる物件
- 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋(マンションは対象外)
- 被相続人が亡くなる直前まで居住していたこと
- 相続開始から3年以内に売却すること
- 一定の耐震基準を満たすか、解体後に土地を売却すること
この特例の適用期限は令和9年(2027年)12月31日まで延長されています。相続後、古家を放置し空き家の原因となっていましたが、この特例が出てからは、税制優遇を活用しようと売却する人が多くなっているそうです。
🔹売却時の条件
- 被相続人の死亡から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
- 売却価格が1億円以下であること
- 売却までに空き家を取り壊すか、耐震基準を満たすリフォームを行っていること
🔹適用されないケース
- 複数人が居住していた家(※1)
- 相続後に賃貸として貸し出した場合
- 1億円を超える売却額
※1:この特例は空き家をなくすことを目的にしていますので、被相続人が亡くなられた時点で一人暮らしの場合に限られます。被相続人に同居者がいなかった場合に限り、亡くなられた方が住んでいた空き家とその敷地を相続された方が売却して利益を得た場合に、その利益から3,000万円の特別控除が認められます。
事例①:親から相続した実家を売却し、特例を適用できたケース
✅状況
-
Aさんは両親が住んでいた一戸建てを相続。
-
親が亡くなった後は誰も住んでおらず空き家状態。
-
築40年の古家付き土地で、固定資産税の負担が大きくなり、売却を決意。
✅売却価格と譲渡所得
-
購入時の価格:1,500万円(両親が購入した当時の価格)
-
売却価格:3,500万円
-
譲渡所得:3,500万円 - 1,500万円 = 2,000万円
✅特例適用の結果
-
3,000万円の控除が適用され、譲渡所得2,000万円が全額控除される。
-
譲渡所得税は0円に!→通常なら20.315%(約406万円)の税負担が発生するところ、特例のおかげで免除が可能。
-
事例②:マンションの場合は特例が使えなかったケース
✅状況
-
Bさんは親が住んでいたマンションを相続。
-
親の死後、マンションは空き家になっていたため売却。
✅売却価格と譲渡所得
-
売却価格:4,000万円
-
購入価格:2,500万円
-
譲渡所得:1,500万円
✅特例適用不可の理由
-
特例は「一戸建て」が対象であり、マンションなどの共同住宅は対象外。
-
Bさんは3,000万円控除を適用できず、譲渡所得1,500万円に対し約20%の税金(約300万円)を支払うことに。
-
◆空き家の解体に対する補助制度
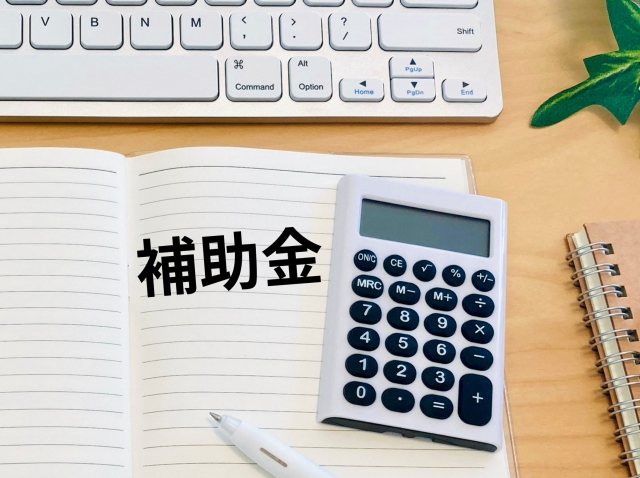
一部の自治体では、空き家の解体費用の一部を補助する制度を設けています。例えば、東京都では空き家の解体費用の2分の1(上限10万円)を補助する制度があります。
注意点としては、自治体によっては補助金がないところがありますので、事前に確認しておきましょう!
◆まとめ
空き家の税制優遇措置は、所有者に適切な管理や活用を促すために導入されています。
しかし、「特定空家等」に指定されると優遇がなくなり、税負担が増加するため、早めの対応が重要です。自治体ごとに補助制度が異なるため、最新の情報を確認し、適切な対策を講じましょう。
日本においては、今後も空き家が増えていくことが見込まれているため、空き家に関する優遇制度や、逆に不利となる措置など出てくることが予想されているため、今後の動きにも注目です。